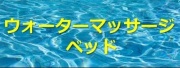最近、身近なところで残念な出来事に度々遭遇します。
“ものごとには、すべてに意味がある”
間接的にも、「なぜこの話を聞くのだろう?」とよく考えます。
相手にどのような声をかけてあげればよいのか?
「大丈夫!」
「あなたなら頑張れる!」
「ちょっと勇気を出してごらん」
相手を励ましたつもりのこの言葉。
逆に自分がなかなか前に進めない時に、こんな言葉をかけられて、つらい思いをしてしまうことはありませんでしたか?
外来をしていると、患者さんからいろいろな悩みを聞きます。
自分なりに患者さんのためになると思って励ましの言葉をかけたりするのですが、逆に相手をもっと苦しくしてしまったり。
患者さんが表情からそういった感情を感じると、相手を理解できない自分がいるような気持ちになります。
他人の気持ちや言葉を理解するためには、経験が必要です。
それは、「痛い思いをする、悲しい思いをする」というきつい経験や、「頑張ったことが結果としてついてくる。人に感謝される」といったうれしい経験かもしれません。
どちらにせよ、人は自分自身が経験したものしか、本当はわからないものです。
つまり、目の前にいる人が、自分の言葉や気持ちを理解できないのは、まだ、そのために必要なことを経験していないのか、自分が相手のことを理解できるような経験をしていないのか。
経験値が違えば、理解にも違いが出てきます。
“自分とは違う相手の存在を認めるということ”
それをわからず、自分の気持ちばかりを伝えるのでは、相手は苦しいばかり。
自分が経験したことがないことを理解することは難しくても、理解しようとすることは誰にでもできます。
そして、お互いが理解し合うためには、わからないからと言って黙っているのではなく、お互いの気持ちも伝え合わなければならない。
そんなことを、ここ最近気付かされているのでしょう。
しかし、この伝え合うということが、実は身近な人にできていないことがよくあるんです。
このことを、具体的に述べておられるのが、「伊藤メソッド」と呼ばれる革新的な勉強法を導入し、司法試験短期合格者の輩出数全国トップレベルの実力を持つ伊藤塾塾長の伊藤真さんです。
深く伝えるためには、言葉を尽くして何度も説明することが必要になってくる。
そしてそれは、近しい関係の方が難しい。
夫婦や親子、友人もそうだし、会社では同僚や上司、部下も近い関係といえるだろう。
近しい人達は、いつも自分のそばにいるから、言わなくてもわかってくれている。
そう思ってしまいがちだが、それは甘えにすぎない。
近いからこそ、実際には伝わっていないことが多いのだ。
小さな不一致やささいな誤解が放置され、だんだんと積み重なって、大きな誤解、大きな不信感につながってしまう。
それがさらに憎しみまでに発展すると、近しい関係であればあるほど、愛情が憎しみに転化してすさまじさを増す。
だから、どんなに親しい関係であっても、相手は自分とは別の存在なのだということを認め合って、尊重する態度を忘れてはいけない。
信頼し合っている近しい関係だからこそ、深く伝えるということを意識して大事にしておきたい。
身近な関係で、ついやりがちな失敗は二つある。
ひとつは言葉が足りなくて、上手く伝わらないという失敗だ。
近い関係なのだから、わかってくれるはずだとか、前に話したから知っているはずだという思い込みがある。
その先入観があるから、伝えようとするときに、どうしても言葉が不足がちになる。
言葉でいちいち説明しなくても、そばにいるのだから伝わっているのだろうという甘えや思い込みゆえに、伝えようという意識が弱くなってしまうのだ。
その結果、こちらが伝えたつもりでも、相手がわかっていなかったり、誤解したままだったりして、溝が深まる。
ふたつ目の失敗は、ひとつ目とは全く逆で、伝えたいという思いが強すぎて、相手に負担になってしまうことだ。
子供に、「テレビばかり観ていてダメじゃないか」とか、「早く宿題をしなさい」と言ってしまう家庭もあると思う。
ところが、子供はちょうどテレビを消して、まさに宿題をやろうとしていた時だったりすると、親から注意されて非常にむくれてしまう。
「今やろうとしていたのに」とカチンときて、やる気をなくしてしまうのだ。
大人でもあるだろう。
ちょうど仕事に取りかかろうとしていたときに、上司から「早くやれ」と注意されると、「わかっているのに、うるさいな」と思ってしまう。
伝える側からすれば、思いを伝えたいという気持ちが勝って、ついくどくなったり、しつこくなったりするので、かえって相手の気持ちを閉ざしてしまうことになりかねない。
近ければ近いほど、その辺の距離感はわかりにくい。
だからこそ一般の人以上に近しい関係では、相手への配慮が重要なのだと思っておかなければいけない。
繰り返すが、深く伝えるためには、どんな関係の人であっても、相手への “思いやり” を忘れてはならない。
「深く伝える技術」 サンマーク出版 伊藤 真
この二つの問題点、私はかなり身に染みるんです。
意見が食い違ったとき、どっちが正しいのか。
こんなとき、実は “どっちも正しい” のかも。
どの考え方にも、その人のおかれた立場、生い立ち、都合、段取り、思いやり、恐怖などが背景にあります。
誰でも自分の中に、それまでの人生でつくり上げた、その人なりの “正しい価値観“ “正しいものさし” を持っています。
どちらのものさしも正しい。どちらにも、正しい理由がある。
そうなったときにどちらが正しいかという議論をしても、決着がつかないことがありますよね。
そう考えると、今の世界情勢、領土問題、政治などがそうかもしれません。
相手の意見を、「ああ、そうだんだ」と一度受け入れてみる。
そうすると相手も、「ならこちらも話を聞いてあげようか」ということにもなるかも。
“受け容れる” と “受け容れられる”
ちょっとこれから少し余裕をもっていこうと思います。
院長 野村