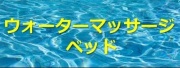只今、春休み中。
子供たちは学校から解放?され、遊びたい気持ちいっぱいなのですが、我が家ではどうもそうはいかないようです。
「やるべきことをやってから!」
何やら想像がつきそうですが、最近もまた夫婦で教育談議を繰り広げることが多くなりました。
私は、全く「勉強しなさい」と言われたことがないので、高校3年になってとても大変なことになりました。
でもよかったと思います。
それは、自分で気付けたから。
「お前ダメだね」と言われていたら、気付く前にあきらめていましたね。
数多くの成功者の方の本を読むのが好きなのですが、みなさん共通するのは、“自己肯定感”がとても強いということ。
巷には、スキル本やノウハウ本でいっぱいですが、結構大事なのは、この“自己肯定感”かも知れません。
自分を認めるという自己肯定感が満たされていれば、事実に目が向くようになるし、他人の言動にもいちいち否定的な反応をしないですみます。
結果、たくさんのチャンスを手に入れることができます。
この“自己肯定感”をどう育めば良いのか、ベストセラー『五体不満足』でおなじみの乙武洋匡氏が持論を述べた本がありました。
四肢のない身体に生まれながらも、前向きに生き、有名大学合格、500万部のベストセラー、スポーツライター、東京都教育委員就任など、数多くのチャンスを得てきた彼が、ご両親にどう育てられたのか、どんな恩師に支えられてここまで来たのか、詳細なエピソードが述べられています。
いまから四十年近くもさかのぼる時代。当時の人々の意識は、「見世物小屋」時代を引きずっていたとしてもおかしくない。
障害のある子どもが生まれても、けっして口外することなく、家に閉じこめたまま、外にも連れださずに育てていたという話も聞いたことがある。
そうした時代に、僕を積極的に外へと連れだし、ご近所さんに見せてまわり、少しずつ“応援団”を増
やしてくれた母の勇気ある行動に、心から感謝している。
僕の両親の子育ては、まさに「ほめて育てる」ものだった。
もちろん、道徳的にまちがった行動をしたときには、みっちりお説教を受けることもあったが、何かが「できない」ことで叱られたという記憶はない。
「それは……あなたが障害者だったからかもしれない」
え、どういうこと?
「あなたが生まれてきたとき、四肢のない身体を見て、『この子は一生寝たきりの人生を送るのかもしれない』と思ったの。それでも、ベッドの上で元気に笑ってさえいてくれたら、それでいいって。そこがスタートだったから、それからはあなたが何をしたって、私たち夫婦にはよろこびでしかなかったのよ」
むずかしいことはわかっている。
それでも、僕らが「平均」や「標準」というモノサシを捨て、その子なりの特性や発育のペースを尊重してあげることができたら──きっと、幸せな子どもが増えていくと思う。
真の厳しさとは、真の愛である。
「もしね、君が万が一、水の事故に遭ったとき、だれかが救助に駆けつけるまで、自力で水に浮いていられるように、せめてそこまでにはしておきたかったんだ」(恩師・高木先生)
「オトくん、ダメなキャッチャーというのはね、打たれたくないという気持ちから、ピッチャーに細かいコントロールばかり要求してしまうんだ。でも、そうするとピッチャーは腕が縮こまって、いいボールが投げられなくなる。反対にいいキャッチャーというのは、『打たれたらオレが責任取るから、とにかく思いきって投げてこい』と言ってやれるの。そうすると、ピッチャーは腕が振れるようになって、かえっていいボールが投げられるようになる」(城島健司選手)
「できないものは仕方ない。その代わり、できることで全力を尽くそう」
障害の有無にかかわらず、自分の弱点をそんなふうに思えたら、どんなにラクだろう。
自分というピースの「へっこみ」ばかりを気にしているから、つらくなる。
もっと自分の「でっぱり」──得意なこと、できることに目を向けていけばいい。
『自分を愛する力』 乙武洋匡 講談社
私の友人は、小学校で一番だったため、中高一貫教育の超進学校に入りました。
ところが、各小学校の一番が集まった学校だったから、彼は突然ビリに転落。
中学一年生でいきなり自信喪失し、立ち直れないまま6年間を過ごしました。
おそらく彼は、超進学校に行かなければ、自己肯定感は保たれたかもしれません。
周りと比べて自分を評価してしまうことが、間違った価値観になってしまうことがあるということ。
娘のテストの点数が悪くても、「よかったね~ 伸びしろがあるじゃん!」
我が家は、超前向きです!
院長 野村