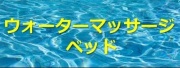ある人が地方都市に旅行し、市役所の人に古くからある神社を案内してもらったそうです。
その神社は50年前に修復を行い、100の会社が協賛、寄付をしてくれました。
さて、50年経った今、そのうち何社が残っていると思われますか、と市役所の人に質問されたところ、
残ったのは、たった1社だったそうです。
では、100年後に生き残れるのはどれくらいかというと、1000社のうち2、3社が定説だそうです。
生存率0.2、3%。
企業という生命体を維持発展させていくことがいかに難しいかをこの数字は示しています。
ちなにみ日本には200年以上続いている会社が3000社あるみたいですが、韓国はゼロ、中国は9社のみ。
何百年も続く老舗を調べると、共通のものがあるようです。
一つは創業の理念を大事にしていること。
その時代その時代のトップが常に創業の理念に命を吹き込み、その理念を核に時代の変化を先取りしている。
二つ目は情熱。
永続企業は社長から社員の末端までが目標に向け、情熱を共有している。
三つは謙虚。
慢心、傲慢こそ企業発展の妨げになることを熟知し、きつく戒めている。
四つは誠実。
誠のない企業が発展した験(ためし)はない。
この4つを大切にしている人と言えば、私はあの京セラの創業者である稲盛和夫さんを思い浮かべます。
今では、売上高1兆円を超える大企業の京セラですが、創業時は大変だったようです。
1955年、鹿児島大学工学部を卒業した稲盛は、京都にある碍子会社「松風工業」に入社。
しかし、入社してみれば、入った会社は、当時すでに銀行管理同然のひどい状況。
おまけにオーナー一族が内輪もめをしていて労働争議も頻発。
入った寮が、これまたひどいあばら家。
一緒に入社した同期5人揃って、「こんな会社早く辞めよう」と言いあうような始末だった。
そして入社した年の秋には、同期もほとんど辞めてしまう。
残ったのは、稲盛を合わせて2人。
しかし、もう一人の同期も、自衛隊の幹部候補学校に入学。
稲盛は転職かなわず、たった一人取り残される。
しかし、進退窮まって、かえって吹っ切れた。
「もうこうなったら、不平不満を言っても仕方ない。ここは気持ちを入れ替えて、徹底的に研究に没頭しよう」。
そう決意した稲盛は、研究室にふとんや鍋を持ち込み、朝から深夜まで研究に没頭。
すると意外なことに、素晴らしい研究成果が出るようになった。
やがて、仕事が認められた稲盛は主任に昇格。
しかし、主任に昇格して3ヶ月目、突然破局がやってきた。
開発責任者として悪戦苦闘していた稲盛に、新任の技術部長が、「君の能力では無理だな。ほかの者にやらせるから手を引け」と引導を手渡したのだ。
外部から来た新任の技術部長のその言葉に、稲盛の頭の血が逆流した。
「あなたこそニューセラミックスが分かるのか。無理というのであれば会社を辞めます」と辞表を叩きつける。
そうすると今度は、辞めることを聞いた部下達が、「一緒に自分達も会社を辞めてついていきます」と言いだす。
前任の上司だった青山まで、「よし、なんとか金を集めて会社をつくろう。稲盛君の上に人を置いたらいかんのや」と大声を張り上げた。
青山には当てがあった。
大学の同窓の友人、京都の配電メーカー、宮木電機製作所の西枝専務と交川常務の二人だった。
青山は、稲盛を連れて西枝専務の自宅を訪れ、これまでの経緯を説明して出資を頼んだ。
しかし、交川常務は「お前、アホか」と青山を一喝。
「この稲盛君がどれほど優秀かしらんが、26、7の若造になにができる」。
しかし青山はひるまなかった。
「稲盛君の情熱は並外れている。必ず大成する」交川も言い返す。
「情熱だけでは事業は成功するのか」。
稲盛も負けずに「将来きっとニューセラミックスの時代がやってくる」と必死に訴えた。
二人は何度も出かけて頭を下げた。そしてついに出資を得ることに成功。
西枝は、「支援するとなったら、とことん面倒をみる」といって、銀行借り入れの際、自宅を抵当に入れた。
この時、西枝は妻に「この家を取られるかも知れんぞ」と断ると、「男が男に惚れたのですから、私はかまいませんよ」と返されたという。
こうして、1959年、わずか28名のメンバーで京セラは連結売上高は一兆円超、従業員数約6万人を擁するまでのグローバル企業になった。
50年前、小さな町工場だった京セラを一躍、世界の京セラへと育て上げた稲盛和夫。
その後、NTT独占だった日本の通信業界に風穴をあけるべく創業したDDI(KDDI)も現在は売上3.5兆円規模の企業となっている。
その情熱は、戦後の日本経済が生み出した奇跡である。
『ガキの自叙伝』 稲盛和夫 日本経済新聞社
京セラは当初「稲盛和夫の技術を世に問うために」作った会社だったそうですが、会社が始まってまもなく、新人社員11人が稲盛さんに団交を申し入れてきたそうです。
連判を押した書状を持ってきて、給料やボーナスを向こう何年にわたって保証してほしい、それぞれ約束してくれなかったら会社を辞める、と言ってきたのです。
この事件は「会社の目的とは何か」ということを考えるきっかけを与えてくれたと稲盛さんは言います。
企業経営の目的とは、技術屋の夢を実現することではない、現在はもちろん、社員やその家族の生活を守っていくことにあるのだと、このとき初めて気づかされ、京セラの目的を「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること」とし、この言葉はそのまま京セラの経営理念となっています。
先週、法事で実家に帰りました。
母が最期のお勤めだと言って、祖父、祖母の50年、父の25年、兄の5年忌を取りまとめました。
そこには母が経営している工場の従業員の方々6名も出席していただいていました。
私の実家は中国山地の田舎町ですが、景気が良かった頃は、田舎町に11社の縫製工場がありました。
しかし、今は母の経営する1社のみ。
しかも、平均年齢は70歳を超えています。
「やっぱり田舎で働く場所を持つということは大事なことじゃけえ、工場は辞められん」
おばあちゃんばかりの工場ですが、社会貢献といって継続している姿は、稲盛和夫さんにも負けていません。
今日は、母の83回目の誕生日。
直接会って「おめでとう」と言えないので、今日は一人で義父の墓に参り、掃除をしながら、母親にはなかなか言えない感謝の気持ちをお義父さんに伝えてきました。
今日は少しばかり素直な息子になれたかもしれません・・・
院長 野村