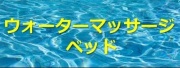今日の外来に、とても味にこだわったお店を出されているご夫婦が来院されました。
月1回の来院ですが、いろいろお話しを聞いていると、どうもお店が流行っていないらしいのです。
詳しく聞くと、同じようなお店が多くなっているのも原因だと思いましたが、味だけは負けないというご主人の自慢のお店を知っていただく努力が必要だと感じました。
ですので、診療そっちのけで、ああしたらいいとか、こうしたらいいとか。
しかし、この世の中、同じようなものが溢れている中で、他とは違う何かを持たなければ、人は気づいてはくれない現実があることを再確認させられました。
当院は、そういったことも意識して、開業当初からスタッフ教育に力を入れています。
みなさんご存じのこのブログも、その一つ。
ところがまだまだあります。
毎朝の朗読会!
わけのわからない文章を違和感がなくなるまで読み続ける。
これは、今までの自分との “違い” を感じるためです。
ここまで聞いても、“この病院のスタッフは可哀そう” なんて思うでしょう。
実は、そうなんです。
院長の要求が多くて、泣きたいくらいなはずです。
でも、みんな頑張っています。
それは、おそらく今までの自分と違う何かを感じているからだと思います。
では、なぜそんなに “違い” を意識するのか。
シンキングマネジメント研究所を設立し、大手企業の幹部等の研修指導にあたっておられる今井繁之さんの言葉もお借りしてお話してみたいと思います。
ホンダの二代目社長の河島喜好(きよし)さんは、「差でなく違いを生かせ!」とよく言っていたという話を、ホンダの関係者から聞いたことがある。
河島さんは、「差というものはいかんともしがたい。人間だって身長が低いからといって高くしようとしても限界がある。企業だって規模が小さいことを嘆いても仕方がない。身長が低いとか企業の規模が小さいと嘆いたところで、その差を埋めるのはむずかしい。 しかし、差を埋めるのではなく、違いを出すことは人間の努力でできるはずだ」という。
たしかに、四輪に進出したころのホンダがトヨタや日産と体力勝負したら負けたはずだ。
トヨタや日産にないものを作ろうと懸命に努力したところに今日のホンダがある。
まさしく「差」ではなく「違い」で勝負したからホンダは成長してきたといえる。
小が大に勝つには自分のところの強みを生かすしかない。
強みなんてあれば苦労しないという人も多いが、しかし、違いによくよく目を向けてみることだ。
必ず強みは見つかる。
『気がきく社員 50のルール』 今井繁之 知的生き方文庫
“差” となると、順位や、規模や、得点など、ほとんどが数量的なもので、縮まるか、広がるかしかありません。
しかし、“違い” は、良い点、悪い点、あるいは特徴など、他と異なっている点であって、それは数量では計れないものです。
人は、たいてい誰かと比べて生きています。
そして、比べる時は、ほとんどが数量的です。
あの人の方がもっと、お金持ちだ、成績がいい、とか。
しかし、人の特徴や、個性などの、特殊性については他人と比べようがありません。
特徴や個性は、好き嫌いといった好みで判断するからです。
企業においては、この他社との ”違い” が生き残るための最大の武器となるでしょうし、医療の現場においても、何が違うのかを患者さんは求めています。
医療の現場でこんなことを意識できるようになったのも、私を今まで育ててくれた2人の個性的な上司のおかげです。
この2人の持っている “違い” は、他とは違う圧倒的なパワーを持っています。
ということで、当院は、これからもお店の経営についても語れる “他とは違った診療” も続けて行きます。
〇〇さん、応援していますので、頑張ってください!
院長 野村