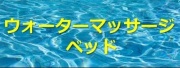そこには、時計がほとんどありません。
そこには、落葉樹がありません。
そこには、自動販売機もありません。
しかし、夢と希望と感動があります。
みなさんご存知、“ディズニーランド” です。
時計が無いのは、時間を忘れて楽しんでもらうため。
落葉樹が無いのは、落ち葉や枯葉から寂しさを連想させないため。
自動販売機がないのは、人のぬくもりを感じてもらいたいため。
人を喜ばせるため、徹底している!
だからまた行きたくなっちゃうんですね。
今の時代だからこそ、機械じゃなく、人の温かさが大切なんです。
この前、東京に行くときに空港の本屋さんで買った本が、
“9割がバイトでも最高のスタッフに育つ ディズニーの教え方”
昨年、過去最高益を出したディズニーランドでは、9割のスタッフが正社員ではなく、アルバイトでアトラクションを運営しています。
しかし、アルバイトでも最高のサービスを提供し、不況にも負けないブランド価値をつくりあげています。
その背景には徹底したディズニーの社員教育システムがあります。
人材レベルの高さといえば、リーッツカールトンとディズニーが有名ですが、
●リッツカールトン:人の「素質」を見極める(=社員のポテンシャル重視)
●ディズニー:どんな人材でも育てることを重視する(=教育重視)
という決定的な差があるのです。
どんなにCS(Customer Satisfaction : 顧客満足度)を高めようとしても、その前段階の社員教育が成功なくしてCSは成り立ちません。
「いつも見ている、マメに声をかけることで相手の存在を認め良好な人間関係を作り、人を育てることは、基本中の基本」
「いつも笑顔で、互いにきちんとアイコンタクトをとって、挨拶を交わしあう」
具体的な方法論、教育カリキュラムもさることながら、職場の人間関係、というもっとも基本的な基盤が良好にできていて、それが伝統のように先輩から後輩へ受け継がれていく。
なかでもすごいのは、清掃担当のアルバイトが自分の仕事を客に尋ねられたときの言葉。
「私達はパークに落ちている思い出のカケラを拾っているんです」
普通の環境であれば、このセリフは濃すぎるかもしれませんが、それをさらっと言える環境があることが、すばらしい。
ディズニーランドで働くことの意味=ミッションを自分なりに消化して行動に移している。
自分で考える、とはまさにこういうことでしょう。
特に目新しい様な教育ノウハウが書かれているわけではなく、むしろ少し考えればわかるような、当たり前のことや基本的なことが多いのですが、しかし“当たり前のこと”こそ、実は最も大切であり、忘れてはいけないものだと思います。
テクニックも大切ですが、“人の心”をしっかり意識することが大切ということ。
この心がけがあるからこそ、何度もリピートされる世界一の夢の空間を想像し得ているのでしょう。
当院も、他院と比べて特別な医療をしているわけでもありません。
しかし、“当たり前のこと”を大切にし、リピートされるクリニックであるために・・・
「私達はこころの底に落ちている元気のカケラを拾っているんです」
今日はちょっとディズニーランドに近づいたな!(自己満足)
院長 野村