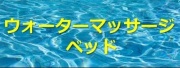気が付けば、ブログが2か月もストップしていました。
言い訳がましいのですが、いつもこのパターンでブログが滞るのは理由があります。
はっきり言って、私は非常に不器用なんです。
一度に多くのことをこなすことができないですね。
ということは、ブログ以外に何かしていたということですが、実は最近すごいものに出会って、大きく価値観が変わってしまったんです。
少し大げさなのですが、今まで漠然を捉えていなかったものが、実は非常に大切だったということに気付いたんです。
医師としてきちんと取り組んだつもりだったのですが、事実、つもりの域を超えていなかった。
非常に反省する一方、覚醒した感があります。
ところで、みなさん佐藤繊維という会社をご存知でしょうか?
米国オバマ大統領の就任式でミッシェル夫人が着用したやさしい風合いの黄色いカーディガン。
世界的ブランド、ニナリッチのカーディガン、それがメイド・イン・ジャパン、しかもメイド・イン・ヤマガタのモヘア糸で編まれたものとわかって大変な話題となりました。
その糸を作ったのが佐藤繊維という会社です。
柔らかい肌触りが特長で風雅な趣から「フーガ」と名付けられたその糸は、アンゴラヤギの毛1グラムを44メートルまで伸ばした極細モヘア糸。
歴史的にも不可能とされてきた極めて細い糸を紡ぐことに佐藤繊維が成功しました。
佐藤繊維の名が広く一般の人々にも知られるようになったのはこの一件がきっかけとなったわけですが、その数年前から繊維業界、アパレル業界ではすでに注目を集める存在となっていました。
快進撃の始まりは2007年のイタリア。
30色のグラデーション糸やウールで和紙を包んだ糸など、独創的な糸をひっさげて世界最大規模のニット用糸見本市に初出展。
すぐにグッチのバイヤーの目に止まり、その後もイブサンローランやランバンから注文が入るようになりました。
ジーンズが千円以下での価格競争を繰り広げているこの時代、有名ブランドであれば数十万円はするニットと同じ糸で編んだ佐藤繊維オリジナルのニットが数万円で大変な割安感をもって買われています。
「高くてもいいものを作る」そんな佐藤正樹社長の信念に時代が追いついてきたのでしょう。
しかし、信念を曲げずに経営を続けていくということはそう簡単なことではありません。
佐藤さんも、ここまでたどり着くまでには、やはり苦労があったようです。
実は、佐藤さんも当たり前にあったものを見方を変えることで、大きな気付きを得た方なんです。
山形に戻って4、5年経った頃でしょうか、私はある糸に魅せられました。
これはどこで作ったのだろうと問い合わせてみたら、取り引きのあったイタリアの工場の糸だと。
自分のところにしかないオリジナルの糸を作る上でヒントを得られるのではないかと思った私は、イタリアに飛びました。
ちょうど世界の糸の最高峰と呼ばれるピッティ・フィラーティー展が開かれていたので、それに合わせて糸を作っていたメーカーを訪問したのですが、この時、私は大変な衝撃を受けたんですね。
人生の一番の転機になったのはこの時だったかもしれません。
驚いたことに、工場に並んでいたのは我が社で使われているのと変わらない機械でした。
その代わり、どの機械にも職人たちが加えた独自の工夫の跡があったんです。
ギアなどの部品を替えたりしながら、独自の糸を作っているわけです。
工場長が親切な人で「この糸を手に取ってご覧なさい」と実際に糸を触らせながら、この糸がなぜここまで美しくなるのか、どうやって製造するのかといったことまで、実に細かく丁寧に説明してくれました。
私の目を見て熱く語る工場長の姿を見ながら、思いましたね。
「ああ、俺たちはアパレルに言われるがままに物作りをやっているけれども、それとは全く別の発想で生きている人だ」と。
そう考えていたら、工場長は「私たちが世界のファッションのもとを作っているんだ」と力強く言うわけです。
この言葉も衝撃的でした。
だって日本でいう工場のイメージは「これを作ってくれ」「はい分かりました」と黙って頭を下げる、というものでしょう。
だけど、この工場長にはそういう雰囲気は微塵もない。
自信と誇りに満ち溢れていました。
「物作りの現場から世界を変えていくことは不可能ではない、自分もこの道を歩いて行こう」と強く思ったのはこの時が最初でした。
日本に帰って、早速社員を集めて「俺たちも人から言われたものではなく、自分たちだけの糸を作ろうじゃないか」と訴えました。
でも反応は冷ややかでしたね。
「社長の息子がイタリアにまで行って変な風邪に感染されて帰ってきた」と(笑)。
いま思うと、新しいオリジナルの製品を作るのも大変でしたが、それ以上にスタッフの心を変えていくのが大変でした。
第一、私が言っていることが正しいとは誰も思っていないわけですよ。
いままでの仕事で食べていけるから、このままで十分という感覚なんです。
だけどバブルが崩壊し、このまま行ったら絶対にこのビジネスはなくなるという危機感が私にはありましたから、ここは意地でも皆の意識を変えないといけないと思いました。
そこで、ある一人のベテラン職人を粘り強く説得しました。
ところが彼の口からは「これだからできない、あれだからできない」とできない理由が次々に出てくる。
イタリアの工場長だったら、そんな理由は言わないはずなのに、と思うと腹立たしくもなりました。
いろいろな人と接していて感じるんですが、物事を成功させる人は「どうやって作るか、どうやったらできるか」という方法を常に考えています。
逆に成功しない人は、できない理由を次々に並べ立てる。
これは要は「作りたいか」「作りたくないか」という問題で、うちのスタッフは全く作る気がないわけです。
「でも絶対に作ってもらわなくては困る」という私の説得に応じて、彼は渋々作り始めたわけですけれども。
それで三か月くらいした頃でしょうか、彼が私の部屋に突然入ってきて、無言のまま机の上にバンと何かを置きました。
それが、なんと新しい糸だったんですね。
私も驚いて、思わず振り返って「できたじゃないか。凄いね」と叫びましたよ。
入社以来何十年もの間、言われたことしかしてこなかった五十代後半の職人が初めて自分で物を考えて、挑戦した。
そうしたらそれができちゃった。
五十代にして物を作る面白さに覚醒したわけですね。
彼はいまも職人のトップですけれども、もし彼が覚醒しなかったら、いま頃会社はなかったかもしれません。
そこから二人での物作りが始まり、今日に至っています。
佐藤繊維 佐藤正樹 「知致」2014年1月号より
当院のスタッフも、最近の院長はおかしいと思っているはずです。
あまりにもテンションが高いので、呆れて辞めてしまわないかと心配しています。
私は妄想癖があって5年から10年先を考えているのですが、そのためか目の前のことがよくわかっていないことが多く、いつも周りに迷惑をかけます。
しかし、最近は1-2年後がはっきりと見えてきているんですね。
これも実は人との出会いのおかげなんです。
佐藤繊維の佐藤さんも、自分からアクションを起こした出会いから大きく人生が変わっています。
やはり、同じ場所から同じものを見ていてはダメです。
何かに行き詰まったら、少しいる場所を変えてみる。
同じものが違って見えるはずです。
ちなみに、先日、以前から行ってみたかった高千穂にある天岩戸神社に行ってきました。
そして、いつものようにおみくじを引いて、今年5個目の “ 大吉 ” を引き当てました。
といっても、行った神社で大吉がでるまで引き続けるのが私流のおみくじの引き方なんですが、子供たちにも、「諦めるな!」と言って、教育のために大吉が出るまでおみくじを引かせます。
不謹慎と思われるかもしれませんが、今年は納得するまで自ら動いて “ 運 ” を強引に引き寄せています。
院長 野村