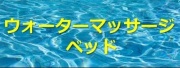昨日、甲子園で行われた試合で、宮崎県代表の宮崎日大は完封負けでした。
当院のスタッフの息子さんが同高の野球部であり、私は広島出身ということもあり、広島カープ出身の榊原監督率いる宮崎日大を応援していました。
結果はともかく、全国レベルまで自らを高めた彼らの努力は、間違いなくこれからの人生の大きく影響すると思います。
しかし、野球のことは全くわからない私なのですが、昨日の監督の采配はどうだったのでしょうか。
試合に勝つことは大切なことですが、これからの人生にとっては勝つことだけが必要なことではないはずです。
何かを目指して挑戦するとき、必ず勝つことも負けることもあります。
彼らが野球をする本当の意味は、勝つために何が必要か、負けた時に何が必要だったかを学ぶことです。
たとえレギュラーになれなくても、ベンチに入れなくても、何を学ぶことができたのか。
それがこれから生きていく上で重要なことです。
私達、大人や親は、子供たちが将来の社会生活できちんと自立できるための学べる環境をきちんと与える必要があります。
このことを理解している指導者がいる組織は、スポーツに限らず、会社でも強いチームワークを築くことができるはずです。
9月にラグビーのワールドカップがあり、これからラグビーも盛り上がっていくと思いますが、日本で最強の大学チームを率いる帝京大学ラグビー部の岩出監督も、その組織づくりにスポーツから何が学べるのかを大切にしている指導者のようです。
その岩出監督の考える指導者の条件とは。
自分がチームをどこに導きたいと考えているのか、その視点がしっかりしていないと何も生まれないと思います。
ただ目の前の勝利だけ見ているのと、学生たちの未来まで見てあげているのとでは、彼らの将来はまるで違ってくるでしょう。
ですから指導者に努力や学習意欲のないチームには未来はありません。
指導者がこれぐらいでいいと考えたところで、学生たちの可能性を摘み、チームの歩みも止まります。
だから指導者は成長し続けなければならないというのが僕の哲学です。
学生はラグビーがしたくて入ってきます。
そこで指導者も同じようにラグビーしか見ていなかったら、たぶんお互いにラグビーのことだけで
四年間は終わってしまいます。
入り口はラグビーでいいと思いますが、指導者が未来をしっかり見据えて指導することで、社会に出て生きる力を育むことができると思うんですね。
僕はいつも学生が卒業する時に言うんです。
この四年間が一番幸せだったと思うような人生にするなと。
卒業後ももっと大きな夢に挑んでほしいと。
人間の脳ってすべてをコントロールするんですね。
しかし現実的なことにすぐ反応して行動の幅を狭めてしまいがちです。
ですから夢を大きく持つことでその幅を大きくするんです。
大きな夢を抱くことによって内に秘められた力を引き出すことができる。
ですから僕は指導者として、若い世代たちの可能性を大きく引き出すような指導者でありたいんです。
大学を出てからもっともっと社会で活躍して、幸せになってほしい。
そのための根を大学の四年間でしっかり培っていきたいと願っています。
岩出雅之(帝京大学ラグビー部監督)『致知』2014年10月号「夢に挑む」
私は、大学時代にラグビー部でしたが、あることを理由に途中で退部しました。
ラグビーが嫌いなわけでもなく、仲間もとても好きでした。
振り返ると6年間継続できなかった心残りはありますが、あの時の自分の置かれた環境では致し方なかったと思います。
メンバーから外されたわけでもなく、自ら外れたわけですので、自分自身でその判断が正しかったと思える生き方をするしかない。
大きな夢を抱くことによって内に秘められた力を引き出すことができる。
今年の夏は、私にも大きな夢をかなえるチャンスがやってきました。
宮崎日大の野球部だけでなく、甲子園に行けなかった野球部の生徒達にとって、試合で負けた経験が将来の大きな目標に繋がる生き方をしてくれることを願っています。
院長 野村