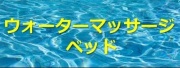患者さんに、食事・運動などの生活習慣のことを説明するたびに、「さて、自分は?」といつも反省しています。
説得力がある自分でなければと、毎日の食事、特に朝、昼はきちんとしていますが、しかし、運動となると…
どんな分野でもそうですが、やはり人の話は何でも経験談が一番説得力ありますね。
だから口コミが非常に大きな影響をもたらすのでしょう。
仕事も教育も、やはり実際にやっている人から言われると違います。
今日は、説得力のある行動について、日本の障がい児教育の先駆者である田村一二さんのお話をご紹介します。
私は六人の息子を持っているわけですが、彼らがまだ小さいとき、どうしても履物をきちんとそろえられなかった。
叱っても、そのときはそろえるが、すぐに元通りに戻ってしまうのです。
それで、私が尊敬する糸賀一雄先生にお尋ねしました。
「しつけとはどういうことですか」と。
先生は、「自覚者が、し続けることだ」とおっしゃる。
「自覚者といいますと?」と聞くと、
「それは君じゃないか。君がやる必要があると認めているんだろう?それなら君がし続けることだ」
「息子は?」
「放っておけばいい」
というようなことで、家内も自覚者の一人に引っ張り込みまして、実行しました。
実際にやってみて、親が履物をそろえ直しているのを目の前で、息子がバンバン脱ぎ捨てて上がっていくのを見ると、「おのれ!」とも思いました。
しかし、糸賀先生が放っておけとおっしゃったのですから、仕方ありません。
私は叱ることもできず、腹の中で、「くそったれめ!」と思いながらも、自分の産んだ子供であることを忘れて、履物をそろえ続けました。
すると不思議なことに、ひたすらそろえ続けているうちに、だんだん息子のことも意識の中から消えていって、そのうちに履物を並べるのが面白くなってきたのです。
外出から帰ってきても、もう無意識のうちに、「さあ、きれいに並べてやるぞ」と楽しみにしている
自分に気がつきました。
さらに続けていると、そのうちに、そういう心の動きさえも忘れてしまい、ただただ履物を並べるのが趣味というか、楽しみになってしまったのです。
それで、はっと気がついたら、なんと息子どもがちゃんと履物を並べて脱ぐようになっておりました。
孔子の言葉に、「これを楽しむ者に如かず」というのがありますが、私や家内が履物並べを楽しみ始めたとき、息子はちゃんとついてきたわけです。
私事で恐縮ですが、ここに教育の大事なポイントの一つがあると思います。
口先だけで人に、「こら、やらんかい」とやいやいいうだけでは、誰もついてきません。
自分が楽しんでこそ、人もついてくるんだという人生観を、私は履物並べから学んだ次第です。
田村一二 『致知』1990年7月号より
全く性格も違う二人ですが、私の実父も義理の父も、好きな仕事をして人に喜んでもらいたいという気持ちが強い人でした。
周りは大変だったと思いますが、結果を出す人達でしたので、だから周りはついていくしかない。
説得力のある二人の父の姿は、今の私の礎になっていることは間違いありません。
今日は、偶然にも亡くなった二人の父の誕生日なので、仏前でお酒をいただくことにしました。
酔っぱらった姿は、娘達には全く説得力はありませんので、飲み過ぎに注意が必要です!
院長 野村