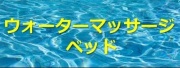夏の甲子園がやってきます。
宮崎は延岡学園に決まりましたが、私は他の高校を応援していました。
実は患者さんの息子さんが強豪校のレギュラーで、話を聞けば、昔ながらのスパルタ指導で、それでも野球が好きだからと頑張ってきたということ。
努力が報われてほしいと思っていましたが、残念でした。
しかし、お母さんは、「この子は、これだけの練習を耐えてきたので、社会に出てどんな苦しいことがあっても耐えられると思います」と、はっきりと言われました。
こういったことは、勉強では絶対身に着けられないものですね。
いいですね。この感覚。
目標を達成することはできなかったけれども、その過程で得たものを大切にする。
今日は、甲子園で春夏連覇を成し遂げた大阪桐蔭高校野球部 西谷浩一監督の野球から学ぶ人間学をご紹介します。
私がここ最近変わったなと思うのは、メンバーから外れた子たちが非常によくやってくれるチームになった、ということですね。
10年ほど前までは夏のメンバー発表が終われば、そこから外れた子は寮を出るのが決まりだったんです。
メンバーから外れて気持ちも少し切れているだろうから彼らは家から通わせるようにしようと。
ところが、私が監督になって3年目の時、皆が寝静まってからキャプテンが相談に来たんです。
「メンバー発表が終わっても、3年生全員を寮に残してほしい」と。
私は内心凄く嬉しかったんですが、理由を尋ねると「監督はいつも、1つのボールに皆が同じ思いになれ、“一球同心”と言われているのに、メンバー外の3年生が寮を出たらお互いに溝ができてしまう。
一球同心が本物にならないと思います」と言ってくれたんですね。
夏のメンバー発表をする時には、背番号をつけてやれなかった子たちがベンチ裏でワンワン泣いているんです。
でも次の日には彼らのほうから「チームのために何かやらせてほしい」と自ら言ってきてくれるようになった。
そして打撃投手をしてくれたりするんですが、私が一番してもらいたいのが相手チームの偵察なんですね。
1、2年生より3年生のほうが野球をよく知っているから、絶対にいい分析ができる。
ただメンバーから外れた3年生にそれを頼むのは非常に酷なことなんです。
その彼らが「偵察にも行きます」と自分から言ってくれるようになり、そこから何かが変わってきた。
3年生の外れた仲間たちがビデオを撮りに行ったとなると、メンバーもいい加減には見られなくなる。
そうしたことで合宿所自体の雰囲気が変わってきました。
今回の甲子園では、決勝戦が1日雨で流れたんです。
メンバーはその日、室内練習場で練習をしますが、宿舎に残っている3年生は部屋で寛いでいてもいい。
ところがその彼らが、決勝で当たる光星学院の一回戦から準決勝までのビデオ4本を全部見直して、
一からデータを取ってくれたんですね。
初めに、負傷した4番の子の話をしましたが、その代わりに入った子が実は全然打てていなかったんです。
でも分析の結果、ワンストライクツーボールというカウントになると、8割以上の確率でスライダーを
投げてくるというデータが取れていた。
そして翌日、1イニング目に彼の打席でそのケースが訪れたんですよね。
私は頭にデータがあったので、スライダーのサインを出した。
そうしたら彼も「分かってるぞ」という顔をしたんです(笑)。
私もスライダー来い、スライダー来い、と念じていたんですが、やってきた球が本当にスライダーで、
それを打ったらホームランで……。
だからあれは本当にメンバー以外の子たちが打たせてくれたホームランで、スタンドにいる子たちも凄く喜んでいた。
たぶん彼らもスライダー来い、スライダー来い、と思っていたんでしょうね。
だから試合に出ていない子の力がいかに大切か、その子たちの力が関わってきた時に、チームは本当の力を発揮するんだなと改めて感じましたね。
西谷浩一(大阪桐蔭高校硬式野球部監督)『致知』2012月7月号
応援していた患者さんの息子さんも、ご両親が野球ができる環境を一生懸命作ってあげられていました。
やはり誰かの支えがあってひとは生きています。
日々忙しさにこういったことも忘れがちになります。
42歳の腰痛持ちの中年オヤジ。
なんだか野球がしたくなりました。(笑)
院長 野村