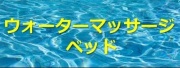宮崎も梅雨が明け、暑い夏がやってきました。
脱水気味の患者さんも多く、外来にて水の重要性についても語ることが多くなってきました。
ところで、暑いと言えば、宮崎の電気店も家電製品の販売競争が熱くなってきましたね。
なかでもK電気とY電気が同じ場所で戦っていましたが、とうとうK電気が閉店に追い込まれました。
同じ電気屋でも違うものを売るなら相乗効果がありますが、安い、多いだけで勝負すれば、どちらかは負けてしまいます。
お互いを高め合う競争ならともかく、自分の利益のみを目的にする考えでは、これからの世の中、物事は成り立たなくなっていくことを証明しているかのような現象でしょう。
いろいろ考えさせられることが日常の生活の中にはありますが、今日は、同じものを売る電気屋でも、何が必要かということをきちんと見極めて仕事をしてこられた東京にある小さな電気屋 でんかのヤマグチの山口 勉さんのお話を紹介します。
地元に大型量販店がくる。
こんな話が私の耳に飛び込んできたのは、町の電気屋「でんかのヤマグチ」が東京都町田市で、創業三十年を過ぎた平成八年でした。
「噂で終わってくれ」と願ったのも束の間、近隣にあっという間に六店もの大型量販店ができたのです。
三十年以上商売をしてきた経験から、売り上げが年に三十㌫近くも落ちることが見込まれ、事実、三、四年の間に借金は二億円以上にまで膨れ上がっていきました。
まさに、会社が存続するか否かの瀬戸際です。
生き残るためにはどうするか。
悩みに悩んで私が出した結論は十年間で粗利率を10%上げ、35%にすることでした。
当時大型量販店の粗利率の平均は約15%で、地元の電気屋が約25%程度でした。
周りからは、「そんなことできっこない」という声が大多数でしたが、それ以外に生き残りの術は浮かばなかったのです。
私がまず決めたのは、大型量販店のように商品を安売りするのではなく、逆に「高売り」することでした。
この頃当店は約三万四千世帯のお客様にご利用いただいていましたが、これだけの数では本当の意味で
行き届いたサービスはできません。
そのため商圏をなるべく狭くし、ターゲットを50代からの富裕な高齢者層に絞り込んで3分の1にまで縮小しました。
そして1万2千世帯のお客様には他店では真似できないようなサービスをとことんしようと決めたのです。
顧客数を3分の1に減らした分、月1度行っていた訪問営業を月3回に増やす。
これによって、お客様との深い人間関係ができ、商品が少々高くても購入してくださる方が増えるだろうと考えたのです。
訪問の際にお聞きするのは、お客様が生活される上でのちょっとしたお困り事についてでした。
ひと昔前の日本では何か困り事があると隣近所で助け合い、支え合うという相互扶助の精神が息づいていました。
私が着目したのはこの部分です。
家電製品のデジタル化が進む一方で、地元民の高齢化もどんどん進んでいました。
当然、家電の操作が思うようにできない方も多くなりますが、お客様のお困り事はそれだけに限りません。
ご高齢、体の不自由な方は買い物に行くのも大変です。
そのため、当店では本業とは無関係なことも徹底してやらせていただくようにしたのです。
お客様の留守中には植木の水やりをしたり、ポストの手紙や新聞を数日保管したり、大雨では代わりに買い物にも出掛けたり。
これらを我われは「裏サービス」と呼び、お代は一切いただきません。
会社のモットーも「お客様に呼ばれたらすぐにトンデ行く」「お客様のかゆいところに手が届くサービス」「たった一個の電球を取り替えるだけに走る」などに定め、「どんな些細なことでも言ってくださいね」とお声がけをしながら10数年、社員パート合わせて50名で徹底して取り組んできました。
ただしお客様との信頼関係は一朝一夕にできるものではありません。
私が粗利率の目標達成期間を1年や2年でなく、10年としたのもそのためです。
悪い評判に比べ、よい評判が広がるにはかなりの時間がかかります。
しかし、この姿勢を愚直に、ひたむきに貫いていったことで、結果的に8年間で粗利率35%を達成することができました。
その目標達成のため、とにかく無我夢中で取り組んできた私ですが、この方向でいけるかなとなんとか思えるようになったのは、粗利率を10%上げる方針に転換して3-4年が経過してからのことでした。
経営者として小さな電気屋が6店舗もの大型量販店との商売競争に勝つためにいったん決断はしたものの、本当にそんな粗利率をクリアできるのか、お客様は本当に買ってくださるだろうか、と悩み続けました。
「この判断は正しい」「いや、ダメだ。うまくいかない」という思いが年中、頭の中で争いをしているような状態……。
しかし、いつも最後には「この道が正しいんだ」という考えが勝ちを占めるよう心掛けました。
肝心なのは一度この道を行くと決めたなら、途中で迷わないことではないでしょうか。
思うように結果が出ないと、あの道もこの道もよさそうだと目移りしますが、そのたびに「成功するまでやってみよう」と自分に言い聞かせる。
急ぐことはなく、ゆっくりでいいからとにかく一歩一歩を着実に歩んでいくことが大事だと思います。
会社の存続が危ぶまれた大型量販店の出現から14年。
しかしこの間、赤字決算が一回もないことには我ながら驚きます。
さらに、一生返せないと思っていた2億円以上の借金を3年前に完済することができました。
人間はとことんまで追い詰められ、地べたを這いずり回るような思いで必死になって取り組むことで
活路が開けるものなのかもしれません。
もしあの時、量販店がこの町田に来ていなければ、今日のような高売りをしているとは考えにくく、そう考えると逆にゾッと寒気すらします。
現在の日本も不況が続き、出口の見えないような状況が続いています。
しかしデメリットばかりに目を向けて内向き思考になってしまっては、せっかく転がっているチャンスも逸してしまいます。
いまある常識やこれまでよしとされてきたことも、本当にこれでいいのか、と根本から疑ってみることで、チャンスが見つかることも少なくないはずです。
現状を打破する発想は、ピンチの中にこそ生まれるのだと思います。
『致知』2012年2月号より
当院の周りにもたくさんの医療機関があります。
では、同じ医療を提供していく中でどのようかたちが必要なのか。
同じ検査、同じ薬でも患者さんの受け止め方は違います。
私達も、いまある常識やこれまでよしとされてきたことも、本当にこれでいいのかと、見直してみることが必要だと感じています。
今の市場原理主義の日本の政治経済にも、小さな電気屋が照らす灯りの大切さを気付く時が近づいているようです。
院長 野村