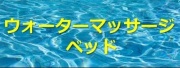一昨日、ついに教師デビューを果たしました!
と言っても臨時講師みたいなものですが、目の前にいる生徒達が、数年後、この知識をしっかり持つことができたら、人を救うことができるのかもしれないと思うと、今までにない気持ちになりました。
私の亡くなった父親、一つ上の兄も教師ですが、改めて生徒達の人生に大きく影響を与える教師という仕事は、とても重要だと感じました。
以前にもブログで書きましたが、“教育が国を創る”と思っています。
人を育てるということも、社会の中でも教育であり、大まかにたとえると人間学の大切さが、これからのとても重要となってくるでしょう。
新人教師として目指す教師像はまだわかりませんが、今日は、私が共感する教育を実践されている伝説の灘校教師 橋本 武さんをご紹介したいと思います。
たとえば試験や課題の提出期限前に一夜漬けの勉強をしなければならないこともありますし、とりあえず目の前のテストなりなんなりに間に合わせなければならないということもあります。
だから、そういった急場しのぎの暗記は仕方がありません。
ただし、そんなふうに付け焼き刃で詰め込んだ知識は、すぐに忘れて使い物にならなくなります。
すぐ役立つことは、すぐ役立たなくなる。
私はそう思うのです。
20年、30年先を見た長期的な学力、能力を身に付けるためには、やはり「「銀の匙授業」でやったように、枝葉にまで疑問をもち、その疑問に対してじっくりと腰を据えて考えるというやり方でないと、なかなか効果は上がらないのです。
中学、高校といった若いときに、とにかく勉強する、一冊でも多くの本を読む、さまざまなことに興味をもつ、いろいろなことについて考えてみる、こういったことをするのは非常に重要なことです。
多感な若いときに受けた刺激、体験した面白さは、形を変えることはあったとしても、何かしら一生心に残るからです。
もちろん、学んだことを全部覚えている必要もないし、そもそもそれは土台無理な話でしょう。
しかし、ときには苦しいけれども読む、書く、そして考える。
そうしてみると、そのときは目一杯でも、あとで「心のゆとり」となって、必ずわが身に返ってきます。
それが“教養”なのです。
きっちりと労力をかけて学んだことは、どこかで必ず役に立ちます。
必要以上に勉強したことがゆとりにつながる。
これが本当の意味での「ゆとり教育」なのです。
戦後の「ゆとり教育」というものは、私に言わせれば「怠け教育」以外の何ものでもありません。
本当のゆとり教育というものは「詰め込み」が重要になってくると思います。
もちろん、受験のための詰め込み教育は問題外です。
ここでいう詰め込みとは、いわば「教養の詰め込み」のこと。
この上積みこそが、受験などという近視眼的な目標ではなく、人生の方々で待ち受ける難問にぶち当ったとき、必ず役に立つわけです。
人間が生きていくかぎり、いろいろなことに直面し、いろいろなことを考えなければならないでしょう。
そうなると、「横道」経験が多ければ多いほど、そうしたさまざまな事態への対応力もより高まるのです。
『一生役立つ学ぶ力』 橋本 武 日本実業出版社
橋本先生は、100歳の現役講師です。
中勘助の小説「銀の匙」一冊を中学の3年間かけて読み込むという前代未聞の授業を行い、公立校のすべり止めに過ぎなかった灘校を名門の進学校に導きました。
いわゆる、「スローリーディング」の授業です。
教え子には、作家の遠藤周作、神奈川県知事の黒岩祐冶、東大総長、最高裁事務総長、等々、日本の各界のリーダーがおられます。
橋本先生は、「横道」にそれることを奨励されています。
「横道」にそれることは、「遊ぶ」こと。
遊ぶように学べれば、色々なものにどんどん興味がわいてきて、自ら調べ、物事を深めることができる。
「横道」経験が多ければ多いほど、不思議に、余裕や、ゆとりができてくる。
教養や、趣味もそうだが、幅広い「遊び」を持っている人は、奥が深くて魅力的だ。
やっぱりワクワクしないことは、いくらやっても本当に意味で身には付きません。
ならばワクワクするような授業をしよう!
ちなみに今日は、パクパクする授業をしました!
さてみなさんに身に付いたでしょうか?
院長 野村